アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。

「この業務は内製すべきか、外注すべきか」。判断を誤ると、短期の成果が出ずに四半期目標を逃すだけでなく、長期的に組織にノウハウが残らず、同じ失敗を繰り返すことになります。この記事では、SaaS企業のマーケティング責任者が、内製と外注の判断をロジカルに下せるフレームワークを提示します。
SaaS企業でマーケティングをリードする立場になると、避けられないのが「リソース不足」の問題です。
採用は時間もコストもかかる。代理店に任せても事業計画に紐づいた成果が出ない。担当者はいるが戦略を描く人材がいない。
そんな状況で必ず直面するのが「この業務は内製すべきか、外注すべきか」という意思決定です。
判断を誤ると、短期の成果が出ずに四半期目標を逃すだけでなく、長期的に組織にノウハウが残らず、同じ失敗を繰り返すことになります。
この記事では、SaaS企業のマーケティング責任者が、内製と外注の判断をロジカルに下せるフレームワークを提示します。読むことで、自社に最適なリソース配分の方針を持ち帰り、即行動に移せる状態になるはずです。
なぜ「内製 or 外注」判断で失敗するのか
多くの企業で、内製か外注かの判断は曖昧な基準で行われています。よくある失敗例は以下です。
つまり、失敗の原因は「判断軸が言語化されていないこと」です。だからこそフレームワークが必要です。
「内製 or 外注」を見極める5つの判断軸
内製か外注かを決めるとき、以下の5つの軸で整理すると判断がブレません。社内稟議でも説明しやすくなります。
この5軸をスコアリング(各軸5段階評価など)し、合計点で「内製」「外注」「併用」の方向性を決めると判断が客観的になります。
SaaS企業における判断の実例
実際のケースでの判断基準の例は以下のようになります。
ケース1:新規チャネル立ち上げ(例:ウェビナー)
差別化度:中/速度:高/資産化:高
最初は外注で立ち上げスピードを確保しつつ、ノウハウを移転して半年以内に内製化するのが現実的です。
ケース2:広告運用(リスティング/ディスプレイ)
差別化度:低/速度:高/資産化:中
運用は外注が合理的。ただしKPI管理やレポート解釈は内製で担保することで、代理店依存を防ぎます。
ケース3:戦略プランニング(チャネル配分設計)
差別化度:高/速度:高/資産化:必須
外注丸投げはリスクが高い。短期成果とノウハウ蓄積を両立するために、ナレッジ移転型の外部支援を選ぶのが適切です。
90日で実行に移す具体的ロードマップ
フレームワークを理解しても、実行できなければ意味がありません。ここでは90日間の実行ステップを一例として提示します。
Day 0–14:業務棚卸し
全てのマーケ業務を洗い出し、5つの軸でスコアリングする。
Day 15–30:優先順位と体制設計
スコアを基に「即外注」「ナレッジ移転型」「内製強化」に区分する。稟議資料にまとめる。
Day 31–60:実行開始
外注領域は契約・運用を開始。内製領域は人員アサインと採用要件定義を整備する。
Day 61–90:見直しとナレッジ移転
定例で成果と課題をレビューし、属人化を防ぐためSOPや教育資料を作成。次四半期に向けてリソース配分を更新する。
この流れに従えば、3か月以内に自社に合った体制の目処が立ちます。
ネクストアクション
SaaS企業のマーケティングにおいて、内製か外注かの判断は感覚や費用だけで決めると失敗します。
5つの判断軸を基にすれば、誰もが納得できるロジックで意思決定できます。特に、事業成長の中核となる戦略プランニング領域は「並走とナレッジ移転型支援」を選ぶことで、短期的な成果と中長期的な資産化を両立できます。
次にやるべきことはシンプルです。
現状の課題を棚卸しし、すぐに打ち手を検討したい方は、以下のリンクから詳細をご確認ください。
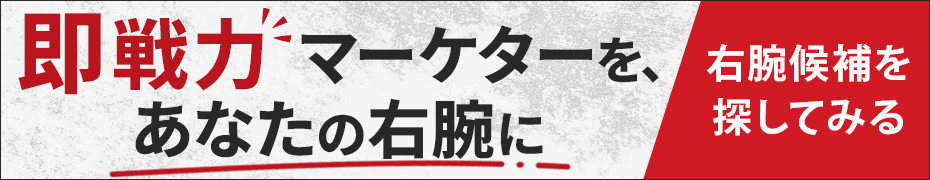
記事を書いた人
アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。
関連記事