アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。
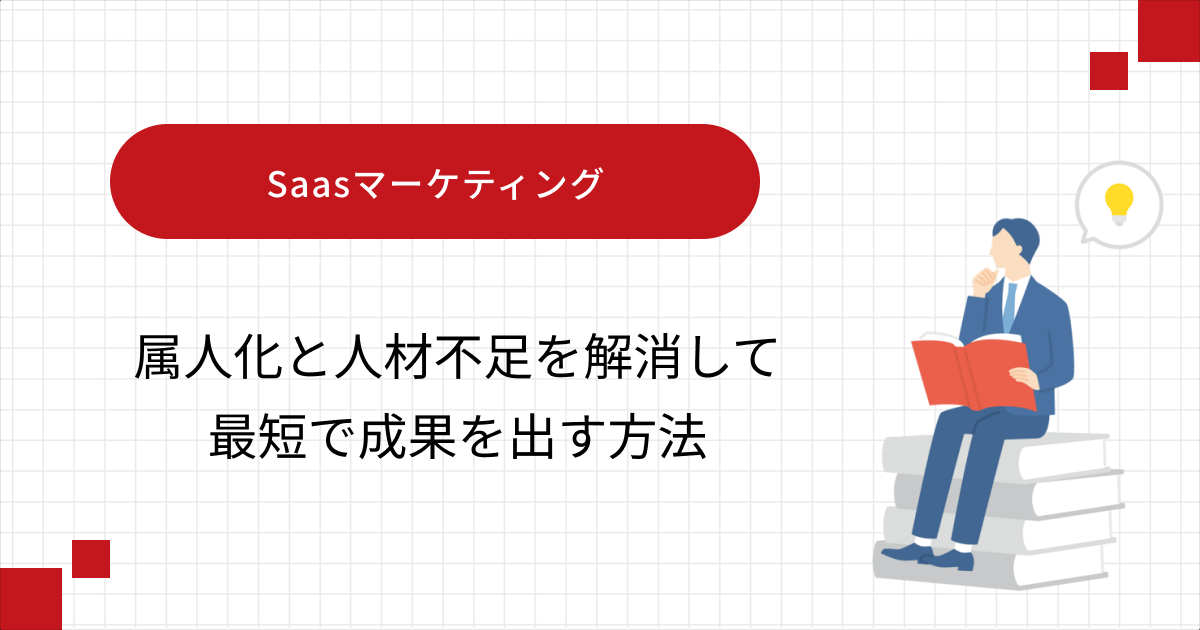
事業は堅調でも、SEOからの新規リードが頭打ちとなり、営業部門からは「見込み客の質が低い」との声が寄せられる状況もあるでしょう。本記事では、こうした課題に直面する担当者へ向け、90日でのSEO施策ロードマップ、内製と外注の判断基準、属人化を防ぐ仕組みづくりを解説し、短期で成果を実感できる解決策を提示します。
SaaS企業が直面するSEO外注失敗と属人化の現実。
IT/SaaS企業では、従業員100〜500名規模にもかかわらず、マーケティング専任が2名以下というケースが少なくありません。
直近でSEO代理店や業務委託を利用したものの成果が得られず、契約見直しを検討する企業も増えています。事業は堅調でも、SEOからの新規リードが頭打ちとなり、営業部門からは「見込み客の質が低い」との声が寄せられる状況もあるでしょう。
本記事では、こうした課題に直面する担当者へ向け、90日でのSEO施策ロードマップ、内製と外注の判断基準、属人化を防ぐ仕組みづくりを解説し、短期で成果を実感できる解決策を提示します。
SaaS企業では、SEO運用(実務+ディレクション)を含め、広告運用、MA(マーケティングオートメーション)、コンテンツ、LP(ランディングページ)改善といった業務が特定の1〜2名の担当者に集中し、業務のボトルネックとなっているケースが頻繁に見られます。
この属人化が、多くの課題を引き起こす根本原因となっています。
SEO関連の案件やToDoが山積しているにも関わらず、インパクトと実行難易度に基づいた整理ができていないため、「広く薄く」手が付けられている状態が生じてしまっています。
これにより、本当に重要な施策に集中できないという問題が発生し、限られたリソースの中で成果を出すことが困難になります。
これまでのSEO外注で失敗を繰り返してきた背景には、いくつかの共通する理由が存在します。
KGI(重要目標達成指標)やKPI(重要業績評価指標)と紐づかないSEO施策の羅列に終始しているため、本質的な成果につながりにくいのです。
提示されるSEOレポートが、具体的な意思決定材料とならないことも問題点の一つに挙げられます。さらに、SEOナレッジが社内に残らず、移管不能な状態となっているため、外注先に依存せざるを得ない状況が続いてしまいます。
これにより、ノウハウが社内に蓄積されず、毎回ゼロからのスタートになってしまうのです。
四半期内での数値改善が必須であるにも関わらず、腰を据えた採用は間に合わず、日々の運用業務で手一杯なため、SEOの戦略設計・振り返り・改善が滞っている状況が深掘りすると、現場の疲弊と役員からのプレッシャーの根源が見えてきます。
経営層からは数値改善を強く求められているのに、現場は目の前の作業で手一杯という板挟みの状態が生まれています。
この章では、90日間でSEO体制を立て直すためのスプリント設計の全体像を提示いたします。
これは、「何からやるか」が一目で分かる優先順位の付け方であり、3ヶ月で何がどこまで改善できるのかという疑問に対する具体的なロードマップとなります。
まず、SEO現状監査を徹底的に実施し、現在の課題を明確に把握します。
具体的には、キーワード分析、競合分析、テクニカルSEO課題特定に加え、チャネル別KPI(主要業績評価指標)、CVR(コンバージョン率)分解、ファネル詰まり特定、計測設定の確認を行います。
次に、SEOバックログ作成&RICE優先度確定の手順を解説し、施策の着手順を決定します。
そして、即効性の高いSEO改善(例:タイトル/ディスクリプション最適化、内部リンク改善)を実践に移し、短期的な成果を目指します。
さらに、LPの3点改善、広告入札/除外キーワードの調整、ナーチャリング分岐(見込み客育成の施策)なども実行することで、多角的に効果を狙います。
SEO運用リズム確立(週次WBR(Weekly Business Review)、仮説→実装→検証のSOP(標準作業手順)化、コンテンツ施策の推進、外部対策)を構築し、安定的な運用を目指せるようにします。
これにより、継続的な改善サイクルを確立することが可能となるでしょう。また、失注した見込み客の再活性施策もこの期間に組み込みます。
最後に、SEOプレイブック作成&ナレッジ移管設計(RACI(責任分担マトリクス)、ダッシュボード雛形)を実施し、社内での知識共有と自走可能な体制を築き上げることを目標とします。
キュメント化を通じて、再現性や引継ぎ容易性を高め、社内にナレッジを残すことが重要です。
属人化を解消するためには、「戦略思考」と「ナレッジ移転」の2つの鍵が必要です。戦略思考により優先順位とリソース配分を定義し、ナレッジ移転により外部リソースを「使い捨て」にせず資産として活用します。
SEOの内製/外注の線引き基準を明確にすることは、失敗を繰り返さないために不可欠です。
どこを自社で担当し、どこを外部に任せるべきかを明確化する判断マトリクスを提示します。
このマトリクスを活用することで、最適な体制を構築できるでしょう。
プロダクト知見が不可欠な差別化の源泉であり、頻繁な意思決定が発生する部分は内製化することが望ましいとされています。
売上やリード数といった目標設定、各チャネルの貢献度可視化、短期・中長期施策の切り分けなど、戦略的な思考が必要な部分です。
専門性が高く標準化が可能で、短期で需要がピークとなるタスク(例:SEOのテクニカル監査、大規模サイトのキーワードリサーチ、競合分析、コンテンツ制作)は、外部の専門家に委託することを検討しましょう。
運用型広告、データ基盤整備、LPのABテスト運用なども含まれます。
SEO外注失敗の再発を防ぐためには、効果的な運用設計が求められます。
KGI→KPI→SEO施策→計測の階層整合性を確保し、SLA(Service Level Agreement:応答/改善サイクル)とナレッジ移転の定義(成果物リスト)を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
これにより、過去に外注で失敗した経験があっても、再発防止できる運用設計が可能になります。必要なのは、成果物やプロセスを資産として残す仕組みです。
SEO業務におけるRACI(責任分担)とスイムレーンの具体的な設定例を通じて、属人化解消の第一歩を踏み出すことが重要です。これにより、誰が何を担うのかが明確になり、効率的な業務遂行が可能となるはずです。
• 役員:KGI/KPI承認(Accountable)。
• マーケティング責任者:優先順位とリソース配分(Responsible)。
• 外部パートナー:実装と検証(Responsible)。
• 社内メンバー:ナレッジ吸収と定例運用(Consulted/Informed→Responsibleへ移行)。
属人化を解消し、リソース不足の中でも成果を出すために、以下の3つの具体的な打ち手を取り入れましょう。
1. 全施策を棚卸しして優先順位をつける
現在行っている施策を「目的」「成果」「リソース消費」の3軸で整理し、継続すべき施策を選定します。この過程で、自社が握るべき戦略的業務と、外部に任せられる作業的業務が明確になります。
2. 会議体を「振り返りの場」に変える
週次の定例会議を単なる進捗報告で終わらせず、仮説の検証と改善サイクルの場にします。「先週の仮説はどうだったか」「どの施策が成果につながったか」「今週は何を試すか」といった問いを共有することで、施策の背景が共有され、属人化を防げます。
3. 成果物を“資産”として残す
提案資料、改善レポート、運用マニュアルなどは使い捨てにせず、再利用できる形で管理します。形式はシンプルで構いませんが、誰が見ても理解できる状態にすることが重要です。
ダッシュボードの「最小」要件を定義することで、チャネル別におけるオーガニック流入→MQL(Marketing Qualified Lead)→SQL(Sales Qualified Lead)→受注のボトルネックを可視化し、改善点を発見しやすくします。これにより、データの活用が容易になり、迅速な対応が可能となるでしょう。
主要KPIの設定と追跡は、成果を測定する上で非常に重要です。SEO関連KPI(検索順位、オーガニック流入数、リード質指標)とチャネル別CVR(コンバージョン率)を定期的に確認することで、施策の効果を正確に評価できます。
その他、CAC(顧客獲得コスト)やリード質指標(適合度/重み付けスコア)も重要な指標です。
社内にSEOナレッジを残し、ドキュメント化や再現性、引継ぎ容易性を高めることは、組織全体のスキルを向上させるための重要な取り組みです。
こうした仕組みを持つことで、担当者が変わっても学習が続き、特定の個人に依存することなく、チーム全体でSEOを推進できる基盤が築かれることでしょう。
属人化を解消し、リソース不足の中でも成果を出すには、スピード感を持って早急に始める必要があります。次の3ヶ月で体制を立て直すために、外部のプロと共に戦略とナレッジ移転の仕組みを作ることを検討してください。
外部パートナーを選ぶ際には、「成果と同時にナレッジを残す設計があるか」を必ず確認することが大切です。外部リソースを活用してすぐに結果を出したいという方はぜひ一度ご相談ください。
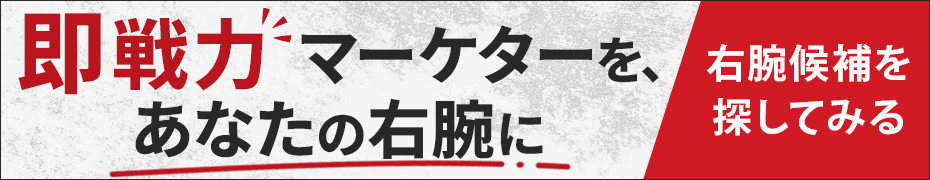
記事を書いた人
アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。