アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。
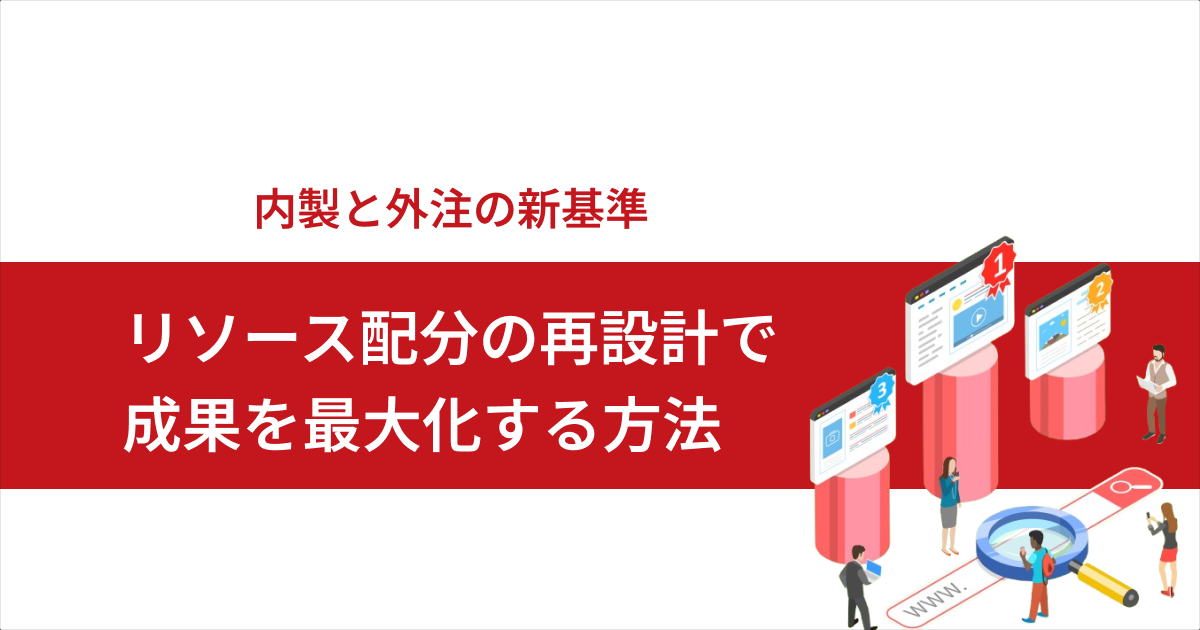
広告依存で伸び悩むIT/SaaS向けに、事業計画起点のチャネル配分と内製/外注の最適化を解説。評価基準とナレッジ移転を前提に、90日ロードマップでPipeline改善へ。
目次
SaaS企業の多くで聞かれる悩みが、「人材はいるのに成果が出ない」というものです。広告やウェビナー、SEOなど施策自体は動いているのに、PipelineやARRが伸び悩む。
原因を「リソース不足」だと考え、慌てて人員を採用したり代理店を追加したりするケースは少なくありません。
しかし実際には、真因は単なる人数不足ではなく 「リソース配分の誤り」 と 「意思決定の属人化」 にあります。
どの施策にどの程度投資するか、内製と外注をどう線引きするか、そのルールが曖昧なまま場当たり的に動いてしまうことで、結果としてコストが増え、成果が見えない状態に陥ってしまうのです。
本記事では、マーケティングリソースを最適に配分するための実践的フレームを提示し、外注を組み合わせた成功事例や90日で実行できる再設計ロードマップを解説します。
これを読むことで、「採用か外注か」の迷いを整理し、自社に最適な意思決定プロセスを描ける状態を目指します。
SaaS企業のマーケティング組織では、広告運用やセミナー開催といった「実務遂行型」の人材は揃っている一方で、事業計画に連動した戦略設計ができる人材が欠けているケースが多く見られます。
結果として、チャネルごとの施策が並行して進むものの、全体最適を欠き「成果がつながらない」状況が生まれます。
例えば、広告は案件獲得数を増やす一方でCAC(顧客獲得コスト)が悪化し、SEOやウェビナーは後回しになる。
こうした偏りは、長期的なPipeline成長を阻害し、リソースの浪費につながります。
多くの企業が頼る広告代理店や制作会社は、実行スピードこそ早いものの、事業戦略との整合性や成果の評価基準を提示する役割までは担えない場合が大半です。
代理店に丸投げし、毎月のレポートを受け取るだけでは「良いのか悪いのか」が判断できず、改善指示も曖昧になります。
結果として、コストだけが積み上がり、経営層に説明できる成果ロジックを欠いたままになるのです。
経営層から「四半期内に成果を出せ」というプレッシャーが高まると、つい広告や短期施策に偏りがちになります。
しかし、それがさらにROIの悪化や長期チャネルの軽視を招き、翌四半期もまた同じ課題を繰り返すという悪循環に陥ります。
ここで必要なのは、短期と中長期を両立するリソース配分のルールを定め、意思決定を属人化させない仕組みです。
リソース配分を考える上で最初に押さえるべきは、短期施策と中長期施策の両立です。
広告や展示会、ウェビナーは短期間でMQL(マーケティングリード)を増やすことができますが、コストがかさみやすくROIが逓減しやすい特徴があります。
一方、SEOやナーチャリング、コンテンツマーケティングは成果が出るまでに時間がかかるものの、Pipelineの安定性を高め、CAC改善に寄与します。
多くのSaaS企業が短期施策に偏りがちですが、長期基盤を同時に育てなければ成長は持続しません。
「即効性×持続性」の両軸で配分を設計することが必要です。
マーケティング業務を「自社で持つべきコア領域」と「外部に委ねられるノンコア領域」に分類することも重要です。
この切り分けが明確になることで、社内人材のリソースを「意思決定」と「ナレッジ蓄積」に集中させられ、属人化を防ぎながら効率的な施策遂行が可能になります。
多くの企業が見落としがちなのが、**「工数と予算の可視化」**です。
たとえば広告には月100時間の稼働を割いているのに、SEOには10時間しか投下していないとすれば、成果が出ないのは当然です。
リソース配分は感覚ではなく、稼働時間や予算を表に落とし込み、KPIとの連動を確認することが欠かせません。
Excelやダッシュボードを活用して「チャネル別の投資額」「担当工数」「成果指標」を一元化することで、次の意思決定が明確になり、経営層への説明力も向上します。
実際に広告依存からの脱却に取り組み、リソース配分を最適化したIT/SaaS企業の事例を紹介します。
あるSaaS企業では、広告に年間予算の70%以上を投下していました。
リード獲得数は一定水準を保てていたものの、CAC(顧客獲得コスト)が高騰し、Pipelineの伸びが鈍化。
さらに広告運用を特定の担当者に依存していたため、退職をきっかけに業務が停滞するリスクも抱えていました。
経営層からは「広告以外のチャネルを強化せよ」との要請が出る一方で、社内には戦略設計ができる人材がおらず、内製・外注の判断も曖昧なまま時間だけが過ぎていきました。
この企業が取った施策は、戦略は内製、実行は外注という切り分けです。
これにより、社内は「方向性の設計」と「成果の評価」に集中でき、外注の成果も客観的にチェックできる体制が整いました。
半年で広告依存比率を50%→35%に削減、新規MQLは前年比で1.8倍に増加。
結果としてPipelineも2倍近く改善しました。
この事例が示すポイントは、外注の成否は「何を任せ、何を残すか」に尽きるということです。
戦略や顧客理解の部分を内製に残すことで、外部パートナーを適切にコントロールでき、短期成果と中長期基盤の両立が可能になります。
広告依存からの脱却や、内製と外注の最適な組み合わせを実現するには、限られた時間でリソースの棚卸しから実行までを一気通貫で進めることが重要です。
ここでは、90日間で成果を示すためのロードマップを紹介します。
まずは現状のリソースを徹底的に洗い出します。
広告、SEO、イベント、ウェビナーなどチャネル別の予算配分、担当者の稼働工数、成果指標(MQL、SQL、Pipeline)を一覧化。
これにより、どのチャネルに過剰投資しているのか/逆に弱すぎるのかが明確になります。
また属人化の有無も合わせて確認し、引き継ぎ不可な領域を特定します。
次に、各施策を「コアかノンコアか」「スピード重視か知識蓄積か」で仕分けします。
その上で、外注パートナーを選定します。この段階では「成果物の明文化」「責任範囲の線引き(RACI)」を契約前に必ず確認することが重要です。
最後の1ヶ月で施策を稼働させ、効果検証サイクルを回します。週次レビューを実施し、KPIツリーに基づいて成果を評価。
うまくいかない施策は素早く撤退し、リソースを再配分します。
この仕組みを90日以内に定着させることで、四半期の終わりに経営層へ「改善の証拠」を提示できる状態を作れます。
外注を導入する際に最も多い失敗は「契約後に思っていた成果が出ない」「社内にナレッジが残らない」というケースです。
これを避けるためには、契約前に評価基準と運用ルールを明確化しておくことが欠かせません。
以下のポイントをチェックリストとして押さえておきましょう。
依頼内容が「運用代行」に留まってしまうと、成果がブラックボックス化します。
契約時点で「何を成果物として受け取れるのか」を明確にすることが重要です。
例えば、KPIツリーやチャネル配分表、施策のスプリント計画を成果物に含めることで、改善の指示や社内展開がスムーズになります。
外注パートナーに完全依存すると、契約終了後にノウハウが消えるリスクがあります。
そのため、ナレッジ移転を前提とした契約設計が必要です。
これらを通じて、知識が社内に蓄積される仕組みを整えることが成功の鍵です。
「成果が出ているのか分からない」という不満は、定期的なレビューがないことが原因です。
最低でも週次レビューを設定し、KPI進捗・改善施策・次週アクションを共有しましょう。
これにより、外注の成果を定量的に把握でき、改善サイクルを主体的に回せるようになります。
本記事では、広告依存からの脱却とマーケティングリソース配分の最適化をテーマに、具体的なフレームワークと外注活用の方法を解説しました。
重要なポイントを振り返ると
つまり、人材不足の本質は単なるリソース不足ではなく「配分と設計の不在」 です。
外注をうまく組み合わせれば、四半期内に成果を出すことは十分可能です。

記事を書いた人
アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。