アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。
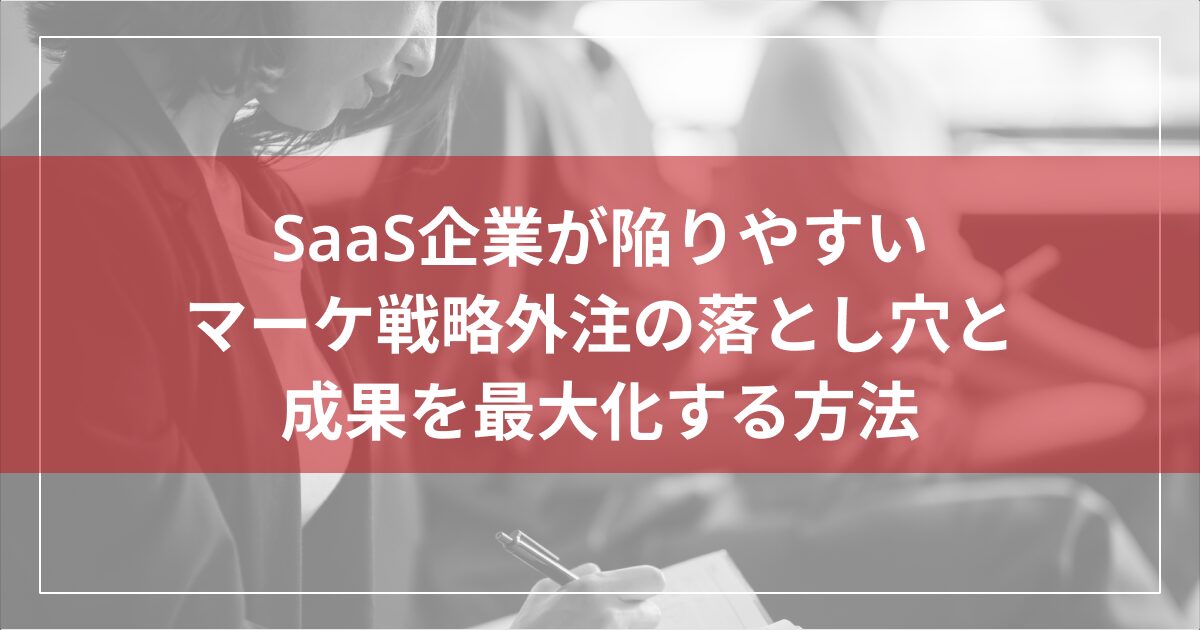
目次
SaaSビジネスは、サービス提供のスピードと継続的な成長が生命線です。
ところが、多くの企業がマーケティング体制の構築に悩み、外部のパートナーに依存せざるを得ない状況に置かれています。
「戦略部分も含めて丸ごと外注すれば効率的に成果が出せる」と考えがちですが、実際には期待した結果が得られず、むしろ負のスパイラルに陥るケースも少なくありません。
本記事では、SaaS企業が「マーケティング戦略の外注」で直面しやすい落とし穴を整理しつつ、外部リソースを賢く活用して成果を最大化する方法を解説します。
さらに、失敗を回避するためのチェックリストや、ネクストアクションも提示するので、ぜひ参考にしてください。
優秀なデジタルマーケティング人材の採用競争は激化しており、特にSaaS業界では経験者の確保が困難な状況が続いています。マーケティング戦略から実行まで幅広いスキルセットを持つ人材は限られており、採用活動に多大な時間とコストをかけても理想的な候補者に出会える保証はありません。そのため外部の専門家に頼ることで、即戦力として機能する体制構築を目指す企業が増えているのです。
SaaS市場では競合他社との差別化が重要であり、マーケティング施策の遅れは直接的に市場シェア獲得の機会損失に繋がります。内製でチーム組成から始めると数ヶ月から1年程度の準備期間が必要ですが、外注活用により1〜2ヶ月で本格的な施策実行に移れる利点があります。特に資金調達後のグロースフェーズでは、投資家からの成長期待に応えるため迅速な体制構築が求められるでしょう。
現代のデジタルマーケティングは多岐にわたる専門領域で構成されており、SEO対策からSNS広告運用、ウェビナー企画、メールマーケティング自動化まで高度な知識が要求されます。各分野で最新のトレンドやアルゴリズム変更に対応するには相当な学習コストが発生し、社内リソースだけでは限界があります。外部の専門業者は日々これらの領域に特化しているため、効率的に成果を生み出せると判断する企業が多いです。
正社員採用では年収に加えて社会保険料、オフィス費用、教育研修コストなど付帯的な経費が発生します。一方で外注契約は月額固定費や成果報酬型など柔軟な料金設定が可能で、事業フェーズに応じてスケールアップ・ダウンできる魅力があります。また短期プロジェクトベースでの契約により、必要な期間のみリソースを確保できるため、キャッシュフロー管理の観点からも有利に感じられるのです。
こうした背景から、「外注すれば解決する」と短絡的に判断してしまうのです。しかし、外注の使い方を誤ると、かえって大きな損失を招くことになります。
SaaS企業が特に陥りやすい落とし穴は以下の通りです。
「自社にノウハウがないから」と戦略からすべて委ねてしまうと、事業理解の浅い外部パートナーに方向性を握られることになります。
結果として、自社の成長モデルと噛み合わない施策にリソースを消耗してしまうケースが目立ちます。外注先は一般的なマーケティング手法に頼りがちで、個別企業の事業特性や顧客ニーズを深く理解するまでに時間がかかります。
このギャップが埋まらないまま施策が進行すると、表面的な数値は向上しても質的な成果に結びつきません。
「半年以内にリードを〇倍にしたい」といった目標を外注任せにすると、持続性のない施策に偏りがちです。
広告に依存しすぎたり、質より量を追い求めるコンテンツ施策になったりするなど、長期的な成長にはつながりません。
特にSaaS事業では顧客獲得から収益化まで一定期間を要するため、短期的な数値改善だけでは本質的な成長は実現できません。外注先も契約期間内での成果を求められるため、即効性のある手法に偏重する傾向があります。
施策の進捗や数値の根拠がブラックボックス化すると、「任せているのに成果が見えない」という不満が蓄積します。
逆に外注先からすれば「必要な情報をもらえないから成果を出せない」というジレンマに陥ることも少なくありません。月次の定例会議だけでは細かな施策調整や戦略修正のタイミングを逃し、結果的に期待していた成果から乖離していく危険性が高まります。
リアルタイムでの情報共有体制が整備されていないと、両者の認識ズレが拡大していくのです。
自社が追うべきKPIと、外注が評価されるKPI(リード数や広告CTRなど)が噛み合わないと、施策がズレていきます。成果の定義が不一致のまま走り続けることは大きな失敗要因です。
外注先は契約で定めた指標の改善に注力するため、事業全体への貢献度を軽視してしまう場合があります。
例えば単純なリード獲得数を重視すると質の低い見込み顧客ばかり集まり、営業チームの負担増加や契約率低下を招く恐れがあるでしょう。
では、外部リソースを効果的に使うにはどうすればよいのでしょうか。失敗を未然に防ぐためのポイントを以下で紹介します。
最も重要なのは、マーケティング戦略そのものを外に出さないことです。
外注先はあくまで「戦術パートナー」として位置づけ、自社の事業戦略に沿った具体的な施策実行を任せる形が理想です。
社内では顧客ペルソナの設定、競合分析、価値提案の明確化、チャネル戦略の策定まで自前で行い、外注先にはその戦略に基づいた実行支援を依頼します。
これにより事業の方向性をぶらさず、外部の専門スキルを最大限に活用できる体制を構築できます。
リード獲得やSEO記事制作などは外注でカバーしつつ、KPI設計や顧客理解に基づく施策判断は社内で担うようにしましょう。このハイブリッド体制が、失敗を最小化し成果を最大化するポイントです。
社内チームは戦略的思考と意思決定に集中し、外注チームは専門性の高い実行業務を担当する役割分担により、それぞれの強みを生かせます。また内製部分を段階的に拡大していくことで、将来的な内製化への移行もスムーズに行えるでしょう。
SlackやNotionなどを活用し、常時コミュニケーションできる環境を整えましょう。
進捗共有を週次・月次で仕組み化するだけでも、認識齟齬を防げます。リアルタイムでの質問・相談ができるチャットツールの導入、共有ドキュメントでの作業進捗可視化、定期的な振り返り会議の設定など、透明性の高い協働体制を構築することが成功の鍵となります。
また施策の背景や意図まで共有することで、外注先の理解度向上と提案品質の改善を期待できます。
施策の成果指標を自社の成長指標に直結させることが不可欠です。
単なる「リード数」ではなく、「SQL数」や「商談化率」など、事業に寄与する指標で合意することが大切です。
外注先の評価基準を事業成果に連動させることで、施策の方向性を事業目標と整合させられます。月次での成果確認時には定量データだけでなく、顧客の反応や市場動向についても議論し、継続的な改善サイクルを回していく必要があります。
外注に任せる際は、SEO・広告・ウェビナー・メールマーケティングなどを「個別」ではなく「統合的」に設計する必要があります。チャネルごとにKPIを切り分けるのではなく、全体で顧客獲得効率を高める視点が欠かせません。
例えば、SEO記事で認知を獲得し、リターゲティング広告で関心を高め、ウェビナーで信頼関係を構築してメール配信で継続的に接点を持つといったシナリオ設計が重要です。各チャネルの相乗効果を最大化する統合アプローチにより、単体施策よりも高い成果を実現できます。
Google AnalyticsやCRM、広告レポートがバラバラに存在していると、正しい判断ができません。ダッシュボードを整備して一元管理し、外注先とも共有することでPDCAを高速化できます。
HubSpotやSalesforceなどの統合プラットフォーム活用により、顧客の行動データから成約に至るまでの全体像を把握し、どの施策が最終的な売上に貢献しているかを正確に測定する体制が必要です。データドリブンな意思決定により、投資効果の高い施策に資源を集中できるようになります。
外注を活用する際は、次のようなチェックリストを使うと失敗リスクを減らせます。
マーケティング戦略の基本要素である市場分析やターゲット設定は、外注に頼らず自社で明確に定義すべきです。
これにより、施策実行のブレを防げます。また、定期的に戦略を見直し、市場変化へ対応できる体制を整えることが重要です。
候補となる外注先の実績や専門分野、リソース体制を詳細に調査し、自社の要求と合っているかを評価します。
成功事例だけでなく、失敗からの学びも確認することで、長期的なパートナーシップの基盤を築くことができるでしょう。
外注先と追求する成果指標を具体的に合意することが不可欠です。事業成果に直結するKPIを設定し、目標達成に向けた報酬体系を明確にしましょう。
定期的な目標見直しの仕組みも契約書に明記するのが望ましいです。
プロジェクト管理ツールや報告形式、緊急連絡体制など、透明性の高い情報共有の仕組みを事前に整えます。これにより、問題の早期発見と迅速な対応が可能となり、プロジェクトの成功確率が高まります。
外注先との協働を通じて、自社メンバーのスキル向上を図る計画を立てるべきです。外注先のノウハウを吸収し、段階的に内製化を進めることで、長期的な競争力強化につながります。
相互成長を目指す関係を築くことが持続的な成果を生みます。
SaaS企業が「マーケティング戦略の外注」で成果を出せないのは、外部パートナーを「丸投げ先」として扱ってしまうことが大きな原因です。
戦略は社内が握り、外注は専門スキルを補完する存在と位置づけることで、初めて外注のメリットを最大化できます。
重要なのは、「どのチャネルに投資するか」「どの指標を追うか」を自社で意思決定できる体制を持つことです。そこを外部に依存しない限り、外注は強力な成長エンジンになります。
成功の鍵は、内製と外注の適切な役割分担、明確なKPI設定、継続的なコミュニケーション体制の構築にあります。
外注先を戦術パートナーとして活用し、自社の事業戦略に沿った施策実行を任せることで、専門性を活かしつつ事業成長を加速できるのです。
マーケティング外注の失敗を避け、成果を最大化するためには、戦略と実行をつなぐ仕組み化が不可欠です。そこでおすすめなのが、マーケティングリソースマネジメント(MRM)を活用したアプローチです。
MRMを導入すれば、外注と内製の役割を整理し、KPIや施策の進捗を一元管理できます。結果として、「外注したのに成果が出ない」という状況から脱却し、マーケティング投資のROIを高めることが可能です。
気になる方は以下のバナーからお気軽にお問い合わせください。
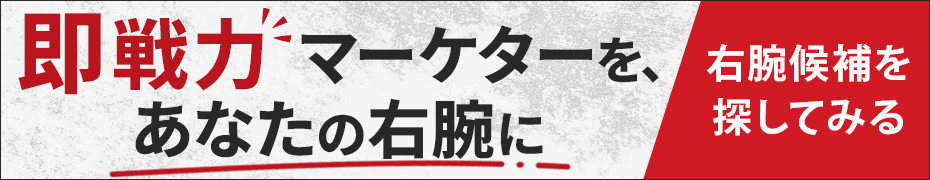
記事を書いた人
アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。
関連記事