アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。

本記事では、繁忙期直前でも間に合うSEOと広告の活用法、そして複数施策を同時進行する際に欠かせない「進行管理のベストプラクティス」を解説します。さらに、教育・人材サービスの実例を交えながら、短期間で成果を出すための改善ステップと運用の仕組み化を紹介します。
目次
新学期や資格試験前、採用シーズンなど、教育業界や人材サービス業界では、集客が「繁忙期」に一気に集中します。
短期間で申込や応募を最大化しなければ、機会を逃してしまう厳しい環境です。
しかし実際には、
こうした悩みを抱えている担当者は少なくありません。
本記事では、繁忙期直前でも間に合うSEOと広告の活用法、そして複数施策を同時進行する際に欠かせない「進行管理のベストプラクティス」を解説します。
さらに、教育・人材サービスの実例を交えながら、短期間で成果を出すための改善ステップと運用の仕組み化を紹介します。
読み終えたあとには、
教育業界や人材サービス業界では、集客の山場が「新学期」「資格試験直前」「採用シーズン」といった繁忙期に集中しています。
そのため、どうしても「短期間で成果が出やすい施策=広告」にリソースが偏りがちです。
一方、SEOは効果が見えるまでに時間がかかるため、繁忙期の直前になると優先度を下げてしまう企業が少なくありません。
しかし、この「SEO後回し」には大きなリスクがあります。
繁忙期前の限られた時間で成果を出すためには、広告・SEO・LP最適化(LPO)・フォーム最適化(EFO)を ひとつの集客フローとして設計すること が欠かせません。
どれか一つに偏るのではなく、広告で短期的に成果を積み上げながら、SEOで中期的な流入の基盤を作り、さらにLPやフォームの最適化で獲得効率を高めることが重要です。
広告はリスティングやSNS広告のように即効性が高く、繁忙期直前の申込・応募獲得に直結します。
一方で配信を止めれば効果も途絶えるため「瞬発力」の施策に過ぎません。
これに対してSEOは成果が出るまでに一定の時間がかかるものの、一度公開したコンテンツが資産化し、次回以降の繁忙期でも安定した流入を生みます。
つまり、広告は短期、SEOは長期という役割を切り分けて考えることが有効です。
繁忙期直前は広告の比重を高めつつ、同時にSEOでも「検索意図直結型コンテンツ」を公開しておくことが鍵となります。
例えば「春期講習 申込」「TOEIC 対策スクール」「転職支援サービス 比較」といったキーワードは、申込意欲が高いユーザーを狙えるため、広告とSEOの双方で押さえておきたい領域です。
ここで重要なのは、広告とSEOをバラバラに扱うのではなく、広告→SEO記事→LP→フォームという一貫した導線を描くことです。
いくら広告やSEOで流入を増やしても、フォームやLPの設計が不十分であればCVRは伸びません。
EFO(フォーム最適化)では、入力項目を必要最低限に減らし、スマホでもスムーズに入力できる体験を用意することが成果に直結します。
LPO(ランディングページ最適化)では、ファーストビューに明確な申込導線を置き、広告と同じメッセージを使うことで一貫性を持たせることが大切です。
ABテストで訴求コピーやCTAの効果を比較すれば、短期間でも改善を積み上げることが可能です。
教育・人材サービスの集客施策は、広告、SEO、イベント、SNSと多岐にわたり、さらに社内部門や外注先が同時に動くことが一般的です。
繁忙期直前にこの複雑な体制を正しくコントロールできなければ、LPやコンテンツ公開の遅延、広告出稿のタイミングずれといったトラブルが起こり、機会損失につながります。
ここでは短期間で成果を最大化するための進行管理のベストプラクティスを整理します。
繁忙期に必要なのは「誰が・いつまでに・どのタスクを完了するか」を明確にすることです。
企画から制作、公開、効果測定、改善までの流れを一元的に管理すれば、進行の遅れを早期に発見できます。
スプレッドシートでの管理では、更新遅れや共有漏れが起こりやすいため、進捗をリアルタイムに見える化できる仕組みを導入することが効果的です。
広告、SEO、イベントが別々の指標で管理されていると、部門ごとの成果は見えても全体の最適化はできません。
そこで重要なのが「共通KPI」の設定です。
たとえばCV数(申込数や応募数)、CPA(顧客獲得単価)、自然流入CVR(SEO経由の成約率)、SOV(検索シェア)といった指標を横断的に追えば、経営層も含めてスピーディーに意思決定ができます。
複数の部門や外注が関わるプロジェクトでは、タスク進捗の可視化や承認フローの自動化が成果を左右します。
マーケティングリソースマネジメント(MRM)を活用すれば、LPや広告素材、記事といったアセットを一元管理でき、更新や差し替えがスムーズになります。
さらに、承認待ちのタスクを自動でリマインドできるため、公開遅延のリスクを大幅に減らすことが可能です。
理論だけでなく、実際の教育業界・人材業界における事例を知ることで、自社の改善ポイントがより明確になります。
ここでは、同じ繁忙期でも成果を伸ばせたケースと、機会を逃してしまったケースを比較し、成功と失敗の分岐点を解説します。
ある学習塾では、繁忙期に向けて「体験授業」や「資料請求」ページを広告とSEOの両方で強化しました。
広告では即効性を重視し、検索連動型広告で「春期講習 申込」など意欲の高いキーワードを狙い、SEOでは同時に「学年別 勉強法」「受験対策の流れ」といった検索意図直結型の記事を公開。
さらにLPには申込ボタンをファーストビューに配置し、EFOでフォーム入力を簡略化しました。
その結果、自然流入CVは前年比30%増、広告CVRも改善し、全体のCV数は1.5倍に伸びました。
ある転職エージェントでは、採用シーズン直前に「業界別 転職成功事例」や「未経験からの転職ガイド」など、候補者の不安を解消するコンテンツをSEOで発信。
同時に広告では「転職エージェント 比較」といった検討段階のキーワードに集中投下しました。
SEO記事と広告LPを内部リンクで結び、ユーザーの動線をスムーズに設計したことで、応募数が従来の1.8倍に増加しました。
一方、ある予備校では繁忙期のキャンペーンに合わせてLPを制作しましたが、部門間の承認フローが複雑で公開が遅れ、広告出稿のタイミングも後ろ倒しになってしまいました。
結果として広告の学習期間が十分に取れず、想定していた申込数に届きませんでした。
もし進行管理を一元化していれば、公開遅延を防げた可能性があります。
別の資格スクールでは、繁忙期に「学習方法まとめ記事」を大量に公開しました。
しかし検索意図が浅く、申込導線やCTAが弱かったため、流入は増えたもののCVには結びつきませんでした。
SEOを「量の勝負」と捉えた結果、商談・申込への転換率が低く、リソースが無駄になったケースです。
繁忙期の施策は「やり切って終わり」ではありません。むしろ、振り返りの質が次回以降の成果を大きく左右します。
教育業界や人材業界のように、集客期が年に数回に集中するビジネスでは、施策を正しく評価し改善点を抽出することが必須です。
繁忙期後は、以下の観点で施策を整理すると、成功要因と改善ポイントが明確になります。
このプロセスを毎回繰り返すことで、「どの施策に再投資すべきか」を判断できるようになります。
振り返りでは、広告、SEO、イベントといったチャネルごとの成果を別々に見るのではなく、同じ指標で横並びに比較することが重要です。
例えば「1申込あたりの獲得単価」で揃えると、広告は即効性があるが高コスト、SEOは低コストだが時間がかかる、といった特徴が一目で分かります。
こうした全体最適の視点が、次回の予算配分の精度を高めます。
多くの企業では、施策の実行までは力を入れても、振り返りの段階で形骸化してしまうことが少なくありません。
ここで有効なのが、振り返りをテンプレート化する方法です。
この仕組みを整えておけば、繁忙期後の振り返りがスピーディーになり、次回の施策改善にすぐ着手できます。
教育業界や人材業界の集客は、繁忙期に成果を出せるかどうかで事業の成長スピードが決まります。
これまで見てきたように、広告だけに依存するとCPAが高騰し、自然流入の比率が改善されないまま次の繁忙期を迎えることになりかねません。
一方で、SEOは「短期では効果が見えにくい」という特性があるものの、繁忙期直前からでも 検索意図に直結したコンテンツ公開やLP改善 を進めれば、申込や応募に結びつく導線を強化できます。
さらに、公開した記事や最適化したページは翌期以降の繁忙期でも資産として効果を発揮します。
この記事で紹介した改善ステップを踏めば、SEOは単なる集客施策ではなく、商談や申込を生む武器に変わります。
もし「短期間で成果につながる仕組みを立ち上げたい」「部門や外注を巻き込んだ進行管理を効率化したい」と考えているなら、MRMの導入が大きな力になります。
戦略設計から実行体制の構築まで伴走支援が可能ですので、ぜひ以下から詳細をご確認ください。
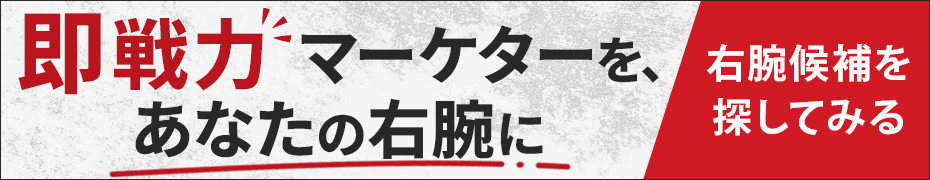
記事を書いた人
アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。