アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。

SaaS企業が直面する「マーケティング人材不足」によるコンテンツ運用の停滞を解決する方法を解説します。マーケティング施策が属人化すると、人材不足が加速し、コンテンツ制作の質と量が落ち込むリスクがあります。本記事では、コンテンツ戦略を仕組み化し、限られたマーケティング人材でも成果を出せる実践的な方法を紹介します。
目次
「人材が足りずコンテンツ施策が止まっている」「担当者が1人に集中し、広告運用や記事制作が回らない」と悩むマーケティング責任者は多いでしょう。SaaS企業において、マーケティング人材不足は成長のブレーキとなりやすく、放置すれば新規リード獲得が停滞します。
本記事では、そのような課題を抱える方に向けて、MRM(マーケティング・リソース・マネジメント)の活用で人材不足をどう補い、コンテンツ運用を成功させるかを具体的に解説します。
SaaS企業では、新規リード獲得や商談創出を目的としたコンテンツマーケティングの重要性が年々高まっています。しかし、実際には「マーケターの数が足りず、記事やホワイトペーパーが計画通り進まない」「属人的に対応していて再現性がない」といった課題を抱える企業が少なくありません。限られた人材で成果を求められる状況は、体制の見直しや仕組み化を急ぐ必要性を示しています。
現在のSaaSマーケティングでは、従来のマス広告とは異なる専門的なスキルセットが求められます。SEO対策、MA(マーケティングオートメーション)運用、ABテストの設計・分析、カスタマージャーニー設計など、多岐にわたる専門知識が必要な一方で、これらのスキルを兼ね備えた人材の市場価値は高く、採用難易度が上昇し続けています。
また、SaaS特有のサブスクリプションモデルでは、顧客のLTV(ライフタイムバリュー)最大化を見据えた長期的なマーケティング戦略が不可欠です。新規獲得から既存顧客の拡張まで一貫したアプローチが要求されるため、マーケターには幅広い知識と経験が必要となり、人材確保がより困難になっているのが現状です。
スタートアップから成熟期まで、企業の成長フェーズでマーケティング人材が直面する課題は異なります。
スタートアップ期には、創業者がマーケティングを担い、組織体制が未整備なことが多いです。ここでは、限られた予算で効果を出しつつ、将来の拡大に向けた基盤を築くことが求められます。
成長期には、売上増に伴い新規施策の要求が高まり、担当者の業務負荷が増大します。この時期は、採用が追いつかない中で、業務の優先順位付けと効率化が最重要の課題となります。
成熟期になると、市場飽和と競争激化に対応するため、高度なマーケティング戦略が不可欠です。データドリブンな意思決定やパーソナライゼーションなど、専門性の高い施策の実行が必要となり、スペシャリストの確保が課題となるでしょう。
マーケ人材不足が続くと、担当者への負荷が集中し、コンテンツの品質や発信量が安定しなくなります。また「誰がどのタスクを担当しているのか不透明」「進行管理が属人化して停滞する」といったボトルネックが発生し、施策全体のスピードが落ちるのも大きなリスクです。
その結果、営業との連携が弱まり、せっかくの投資が成果につながらない状況に陥る可能性もあります。
属人化が進行すると、個人の頭の中にノウハウが蓄積され、組織としての学習効果が薄れてしまいます。
特にSaaSマーケティングでは、顧客セグメント別のメッセージング、チャネル別の最適な配信タイミング、コンテンツの成果測定方法など、継続的な改善により蓄積されるナレッジが競争優位性の源泉となるため、この情報が個人に依存している状態は大きなリスクといえます。
また、キーパーソンの離職や異動により、これまで培ったナレッジが失われるリスクも無視できません。特に成長期のSaaS企業では人材流動性が高く、重要な知見を持つメンバーの退職により、マーケティング活動が一時的に停滞するケースも散見されます。
属人化が進むことによって、同じ種類のコンテンツでも担当者によって品質や成果が大きく異なる状況が生じやすくなります。例えば、ブログ記事の執筆において、1人の担当者が作成した記事は高いエンゲージメントを獲得する一方で、別の担当者の記事は期待した成果が得られないといった現象が発生しがちです。
この問題は、組織全体のマーケティングROIを押し下げる要因となります。成功事例を横展開できない状態では、限られたリソースを最大限活用することができず、結果的により多くの人員が必要となる悪循環に陥る可能性があります。
属人化されたマーケティング体制では、事業成長に応じたスケールアップが困難になります。新たな市場への参入や新製品のローンチ時に、既存の担当者が対応しきれず、機会損失が発生するリスクが高まります。
また、属人化により業務プロセスが標準化されていない状態では、新しいメンバーのオンボーディングに時間がかかり、即戦力としての活用が難しくなります。これにより、人員増強を図っても期待した効果が得られない状況が生じやすくなるでしょう。

こうした課題に対し、近年注目されているのが MRM(Marketing Resource Management) の活用です。
MRMは、マーケティングの計画・リソース配分・進行管理・成果測定を一元化できる仕組みで、人材不足や属人化を解消する強力な手段になります。
具体的には以下のメリットがあります。
MRMシステムは、プロジェクトの全工程を一目で把握できるメリットがあります。各担当者がどのタスクにどの程度の時間を費やしているか、どの工程でボトルネックが発生しているかをリアルタイムで確認可能です。この可視化により、業務量の偏りを早期発見し、タスクの再配分や優先順位の調整を迅速に実行できます。
また、プロジェクトの進捗遅延が予測される場合には、自動アラート機能により関係者に通知され、適切な対応策を講じることができるでしょう。結果として、特定の担当者に負荷が集中することを防ぎ、チーム全体での効率的な業務遂行が実現します。
MRMでは、成功したコンテンツ制作プロセスをテンプレート化し、標準的なワークフローとして保存できます。
記事作成であれば、テーマ設定から執筆、校正、承認、公開までの各段階で必要な作業項目や品質基準を明文化し、誰が担当しても同じレベルの成果物を作成できる環境を構築します。過去の成功事例で使用されたキーワード選定方法や構成パターン、効果的な画像素材なども合わせて保管することで、新規メンバーでも即座に高品質なコンテンツ制作に参加可能です。
このテンプレート活用により、属人的なスキルに依存しない安定したコンテンツ品質を維持できるようになります。
MRMは各マーケティング施策にかかったコストと獲得した成果を自動的に紐づけ、ROIを算出します。
コンテンツ制作に投じた人件費や外注費、広告配信費用などの総コストと、獲得したリード数や売上への貢献度を明確に関連付けることで、どの施策が最も効果的だったかを数値で判断できます。この定量的なデータは、予算配分の最適化や今後の戦略立案に活用できるだけでなく、経営陣への報告資料としても説得力のある根拠となるでしょう。
MRMによって、感覚的な判断ではなく、データに基づいた合理的な意思決定により、マーケティング投資の正当性を明確に示すことが可能となります。
このように、MRMを導入することで「限られた人材で最大限の成果を出す体制」を整えることが可能になります。
MRMを効果的に取り入れるためには、段階的な導入が有効です。
この流れで導入することで、現場の混乱を避けながらスムーズに定着させられるでしょう。各フェーズについて、以下で解説していきます。
MRM導入の最初のステップは、現状のマーケティング業務を分析し、課題を明確にすることです。ここでは担当者にヒアリングを行い、日々の業務で感じる課題や、最も時間がかかる作業、情報連携の悩みなどを洗い出します。
同時に、使用中のツールやシステムを整理し、重複や非効率な運用がないか確認します。多くの場合、部門や担当者ごとに異なるツールが使われ、データの分散や二重入力といった無駄が生じています。
また、過去1年間のマーケティング施策を振り返り、企画から実行までの期間や投入リソース、成果を分析し、効率性やROIの改善点を探ります。これにより、MRMで優先的に解決すべき課題が明確になるでしょう。
続いて、現状分析に基づき、MRM導入で最も効果が期待できる領域を特定します。優先順位付けには以下の基準がおすすめです。
まず、現在のボトルネックとなっている業務を最優先としましょう。例えば、コンテンツ制作の承認フローが複雑だったり、広告運用のレポート作成に時間がかかったりする業務です。
次に、属人化が進んでいる業務で、標準化による大きな改善が見込める領域を選びます。特定の担当者しか対応できない業務は、その人員が不在になるとリスクが高まる可能性があるため注意が必要です。
さらに、成果測定が難しい領域も候補になります。MRM導入で可視化が進めば、これまで見えなかった改善点を発見できる機会が増えるでしょう。
そして、各領域について導入前後の具体的な目標値を設定します。例えば「コンテンツ制作期間を平均20日から15日に短縮」「月次レポート作成時間を8時間から3時間に削減」のように、定量的な指標を用いることが大切です。
選定した優先領域で、MRMの限定的な導入を開始します。これは、リスクを抑えながら実際の効果を検証することが主な目的です。
パイロット導入では、協力的なチームメンバーと小規模に始め、システムの操作性や業務フローとの相性を確認します。初期段階では想定外の課題も発生しやすいため、柔軟に対応できる体制を整えることが大切です。
効果検証では、事前に設定した目標指標がどの程度達成されたかを定期的にモニタリングし、改善効果を数値で把握します。また、利用者からのフィードバックを積極的に集め、システム設定の調整や業務プロセスの見直しを継続的に行っていくのです。
パイロット導入で効果が確認できたら、対象範囲を段階的に広げていきます。全部門に一気に展開せず、関連性の高い領域から順次拡大することで、混乱を最小限に抑えることが可能です。
拡張段階では、パイロット導入で得た知見やベストプラクティスを活用し、効率的に導入を進めます。また、導入済みの部門メンバーが新規部門をサポートする体制を作り、組織内のナレッジ共有を促進します。
全社展開後も、定期的な効果測定と改善を続け、MRMの価値を最大限に高めることが大切です。技術や事業環境の変化に応じて、システムの機能追加や業務プロセスの見直しを継続的に実施することで、持続的な競争優位性を確保できるでしょう。
こちらでは、マーケティング人材不足に直面する企業がどのように行動を起こすべきか、そのステップを整理して解説していきます。成果に繋げるべく、すぐに取り入れられる実践的な手法から始め、次に中期的な視点でリソースを整備し、最終的には組織全体の仕組みを変革する流れを紹介していきます。
読了後すぐに取り組むべき具体的なアクションとして、まずは現在の業務プロセスを1週間程度詳細に記録することから始めましょう。各担当者が日々どのような業務にどれだけの時間を費やしているか、どの工程で待ち時間や手戻りが発生しているかを把握することで、改善の糸口が見えてきます。
次に、現在使用中のツール類をリストアップし、それぞれの利用頻度と満足度を評価してみてください。重複機能や使い勝手の悪いツールを特定することで、MRM導入時の統合対象や改善ポイントが明確になります。
1-2ヶ月以内に実施すべき取り組みとして、社内のステークホルダーとの対話を通じた課題認識の共有があります。マーケティング部門だけでなく、営業部門や経営陣とも現状の課題について議論し、改善の必要性について共通認識を醸成することが重要です。
また、MRM導入の成功事例について情報収集を行い、自社の状況と類似した企業での活用方法を研究することで、より具体的な導入計画を策定できるようになります。業界セミナーへの参加やベンダーとの情報交換なども効果的な情報収集手段といえます。
MRM導入は単なるツール導入ではなく、組織文化の変革を伴う取り組みでもあります。データに基づく意思決定の重要性や、標準化されたプロセスの価値について、組織全体で理解を深める必要があります。
この文化変革を円滑に進めるためには、変革推進チームの組成や、変革に積極的なメンバーの巻き込み、継続的なコミュニケーションの実施などが不可欠です。長期的な視点で組織の変革力を高めることが、MRM導入成功の鍵を握っているといえるでしょう。
SaaS企業の「マーケ人材不足」は深刻な課題ですが、適切な仕組みとツール導入により解決可能な問題です。特にMRMは、限定リソースの最大活用と属人化防止を両立しながら、継続的な成果創出を支援する実用的なソリューションとなります。
重要なのは、採用強化だけでなく既存リソースの最適化という視点です。MRM活用により、少数精鋭でも高い成果を実現する組織体制構築が現実的な解決策として浮かび上がりました。
成功要因は段階的導入アプローチと継続的な改善活動にあります。大規模変革ではなく、小さな成功の積み重ねによる組織能力向上が、持続可能な競争優位性確立への道筋となるでしょう。今日から実践可能な現状把握と課題整理を起点として、自社最適なMRM活用の道筋を描くことをおすすめします。
「記事を読んでMRMの効果は理解できたが、実際の導入方法がわからない」「自社に最適なMRMソリューションを知りたい」とお考えではありませんか?
私たちは、SaaS企業のマーケティング人材不足解決に特化したMRMサービスを提供しています。貴社の現状課題を詳しくヒアリングし、最適な導入プランをご提案いたします。
まずは以下のバナーから、貴社のマーケティング課題について気軽にご相談ください。
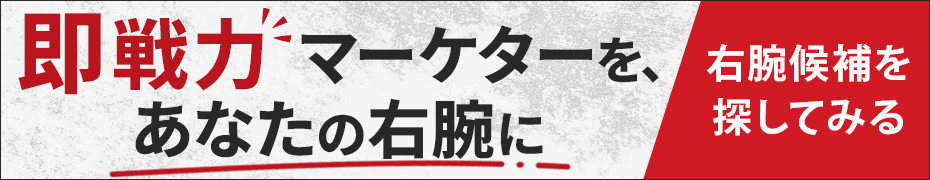
記事を書いた人
アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。