アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。
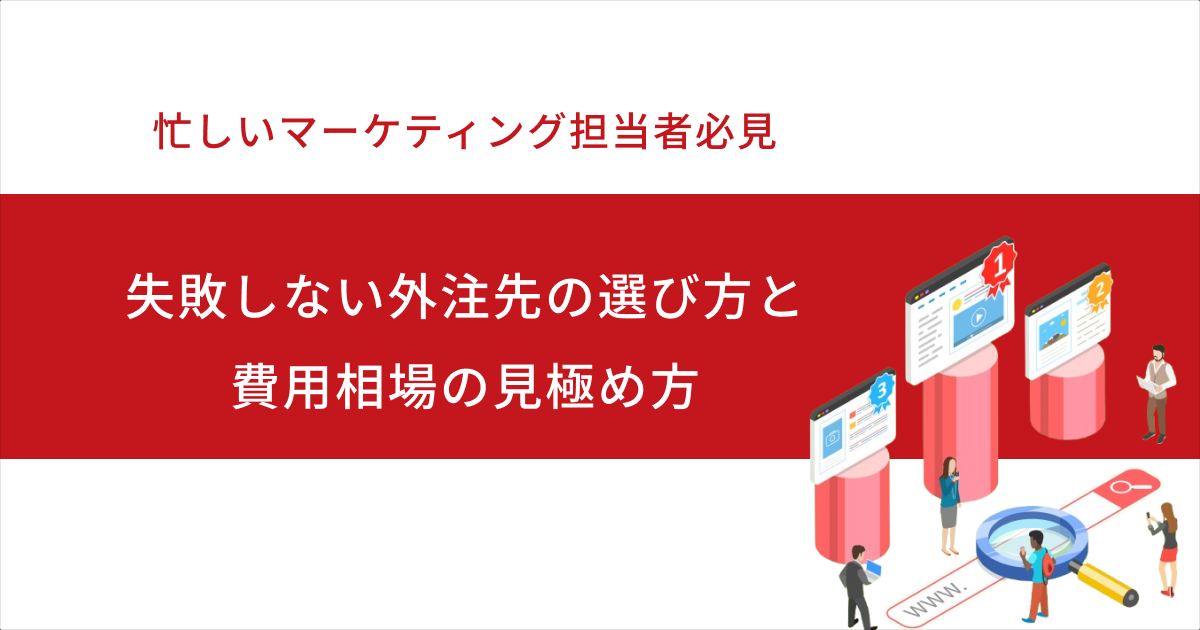
目次
「社内でマーケティングを強化したいけれど、リソースも知識も足りない」
「外注の費用はどれくらい?効果は出るの?」
そんな悩みを持つマーケティング担当者や経営層の方は、今や珍しくありません。広告運用、SEO、SNS運用、LP制作…。やるべきことは多岐にわたる一方で、すべてを内製化するのは現実的ではないというのが多くの企業の本音です。
そこで重要なのが、成果につながる外注先の見極め方と、費用対効果の高い施策の選び方です。
本記事では、マーケティング業務の外注を初めて検討している方や、過去に外注で失敗した経験のある方向けに、外注の判断基準・費用相場・選定ステップを実践的に解説します。
企業のマーケティング領域はここ数年で急速に複雑化しています。
こうした背景から、外部パートナーを活用しながら“戦略的にリソースを補完”する企業が増えています。
ただし、“何でも丸投げ”ではなく、「何を誰にどう任せるか」の判断が成果の分かれ目になります。
| 失敗パターン | 原因 |
|---|---|
| 安さだけで外注先を選ぶ | 提案力や改善力が乏しく、成果につながらない |
| 明確なゴール設定がない | 「何のために」「何をもって成功か」が曖昧 |
| 丸投げしてしまう | 目的共有が不十分で、期待とのズレが生じる |
| コミュニケーションの質が低い | 報告・改善提案がなく、関係が形骸化する |
業務ごとに費用の目安は異なります。以下は法人・フリーランスそれぞれの相場と、比較すべき観点です。
| 業務カテゴリ | 法人相場 | フリーランス相場 | 比較の観点 |
|---|---|---|---|
| 広告運用(Google/SNS) | 月10〜50万 | 月3〜15万 | KPI設計/改善提案/成果報酬型の有無 |
| SEO・コンテンツ制作 | 月15〜50万 | 月3〜15万 | 専門性/構成・分析力/納品体制 |
| LP・バナー制作 | 10〜100万 | 5〜40万 | UI/UX設計力/A/Bテスト支援 |
| SNS運用・管理 | 月10〜30万 | 月3〜10万 | 投稿企画/分析/ファン育成力 |
| Webコンサル・戦略立案 | 月10〜50万 | 月10〜30万 | 課題抽出力/戦略設計/体制提案 |
相場は“金額”だけでなく、“何が含まれているか”を基準に見ることが重要です。
| 観点 | 外注が向くケース | 内製が向くケース |
|---|---|---|
| 目的 | 短期成果を求める | 長期的にノウハウを蓄積したい |
| リソース | 人材・時間が足りない | 育成余力・社内体制がある |
| 施策 | 専門性が高く最新知識が必要 | 継続的なルーティン運用 |
成功企業は以下を徹底しています:
マーケティング外注は、リスクではなく戦略的リソース活用です。
判断を誤らなければ、限られた予算でも高い成果を生み出すことができます。
選ぶ基準、準備すべきこと、比較の観点を持ち、「選べる側」になりましょう。
そして必要なら、第三者の専門家の力も、賢く活用してみてください。
記事を書いた人
アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。