アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。
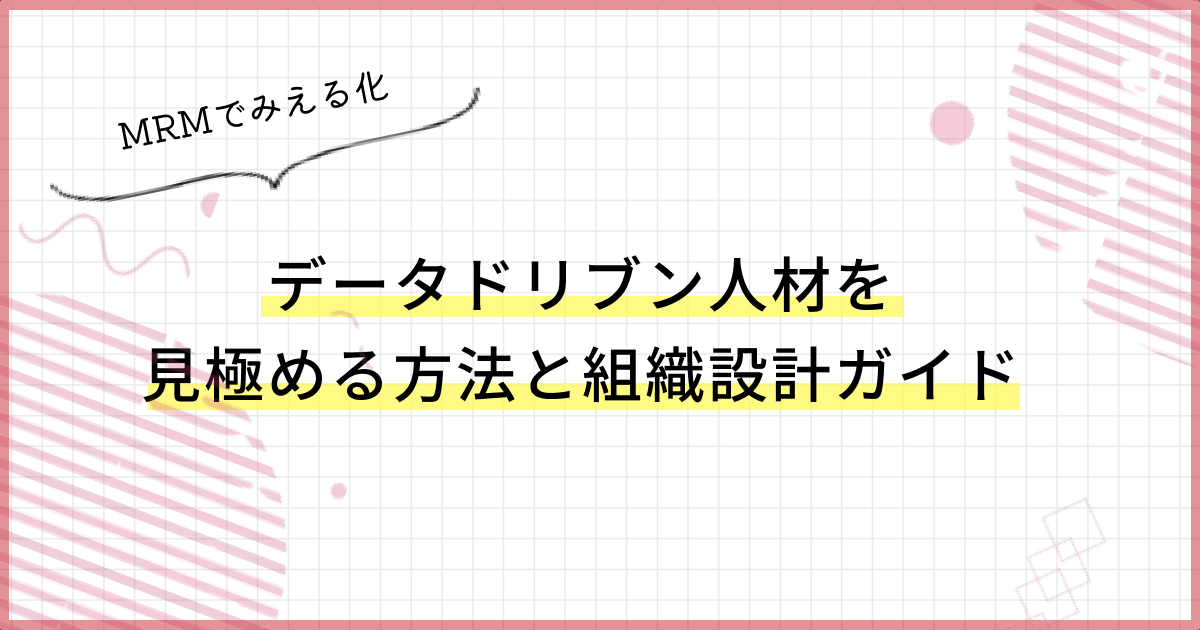
IT/SaaS企業の人材不足の本質は人数ではなく「戦略人材不在」と「データドリブン欠如」。要件定義・リソース配分設計・外部支援活用で四半期内に成果改善を実現する方法を解説。
目次
「マーケティング人材を採用したのに、成果が出ない」──IT/SaaS企業でよく耳にする声です。
その背景には「人が足りない」という単純な課題だけでなく、求める人材像を明確にできていないことが大きな原因として存在します。
特に成長フェーズのSaaS企業では、広告運用やイベント企画など“手を動かす人”はいるものの、データを根拠に戦略を描けるマーケターが不在になりがちです。
本記事では、そうした課題を抱えるマーケ責任者に向けて、以下を解説します。
読み終えたときには、要件定義のドラフトと実行計画のイメージを手にできるように設計しています。
SaaS企業の成長フェーズでは、明確な数値目標を短期間で達成することが求められます。
しかし、従来の「広告運用に強い」「イベントが得意」といった部分的スキルでは、事業計画に直結する数字責任を担うことが難しいのが現実です。
マーケ担当者が個別施策を進めても、それが事業計画やPL(損益計算)にどう寄与しているかが説明できなければ、経営層を納得させられません。
結果として「とにかく施策を打て」という指示と「本当に成果は出ているのか?」という不信感が同時に生まれ、組織全体が消耗してしまいます。
これらはすべて、データを基盤に意思決定できる人材がいないことに起因します。
データドリブン人材の本質は、単に数字を集めることではなく、数字を意味のあるストーリーに変換できるかにあります。
たとえば、MQL数が増えていても、SQL率や受注率が下がっていれば意味はありません。
データを部分的に見るのではなく、ファネル全体を俯瞰して因果関係を紐解く視点が不可欠です。
また、データを読み解くだけでなく、次のアクションに落とし込む力も求められます。
たとえば「広告からのMQL獲得単価が高騰している」という事実に直面したとき、即座に「SEO強化にシフトすべきか」「LPのCRO改善を優先すべきか」といった打ち手に変換できることが重要です。
CRO(Conversion Rate Optimization)は、単なるデザイン改善ではなく、ユーザー行動をデータで裏付けながら仮説検証を繰り返す営みです。
ヒートマップやA/Bテストの結果を分析し、最も効果の高い施策をスピーディに実装する。この「実験思考」がなければ、成長スピードは鈍化してしまいます。
さらにCRMの活用も、SaaS企業では必須スキルの一つです。
単なる顧客データベースではなく、顧客ステージごとの接点管理やLTV最大化戦略に直結するプラットフォームとして運用できるかが問われます。
CRMを使いこなすことで、マーケティング活動が単発施策の集まりから、顧客ライフサイクル全体を設計する仕組みへと進化します。
最後に欠かせないのは、データを経営目線で語れる力です。
単に「CVRが上がりました」「クリック率が下がりました」といった施策単位の数値ではなく、「Pipeline創出に◯件寄与し、ARRで◯◯百万円インパクトが見込める」と翻訳できる力が求められます。
この視点を持つ人材であれば、経営層への報告もロジカルになり、意思決定のスピードを加速させることができます。
まさに「データを語れる」ことが信頼と成果の分かれ目となるのです。
採用要件定義を成功させる第一歩は、その人材が組織に入ったときに果たすべき役割を明文化することです。
たとえば「データ分析ができる人」と書くだけでは抽象的すぎて候補者も自社もミスマッチを招きます。成果に直結する役割目的を記載することで期待値が揃いやすくなります。
次に重要なのは、成果をどの数値で測るかを要件に含めることです。
「リード獲得数」や「広告クリック率」だけでなく、事業成長に紐づく指標を明記すると、採用後の評価基準としても機能します。
これにより「データをどう動かせば成果になるのか」という視点を持った候補者を見極めやすくなります。
よくある失敗は、求人票に「必要なもの」を並べすぎて完璧人を探してしまうことです。
たとえば「CROの経験が必須」「CRM運用の経験が必須」と列挙すれば、母集団は極端に狭くなってしまいます。
そこで 必須スキル(最低限必要な条件) と 歓迎スキル(あると望ましい条件) を明確に分けることが重要です。
例を挙げると、必須スキルは「データを事業目線で語れる力」「CRMを使った顧客管理経験」。
歓迎スキルは「CROツールを用いたテスト設計経験」「BIツールを用いたレポーティング」といった形です。これにより、採用市場で現実的かつ効果的に人材を集められるようになります。
もうひとつのポイントは、スキルだけでなく行動特性を要件化することです。
たとえば「2週間以内に現状データを棚卸し、仮説を提案できる」「経営層への報告を自ら設計・実施できる」といった、行動ベースで測定可能な基準を盛り込むことで、オンボーディング時の期待値がズレにくくなります。
マーケティング責任者の多くが陥るのが、「全部を内製化したいが、時間がない」「外注に任せたいが、どこまで依頼すべきか分からない」 という迷いです。
この曖昧さが続くと、採用も外注も進まず、結局リソース不足のまま四半期を終えてしまうことになります。
したがって、内製と外注を切り分けるフレームを持つことが不可欠です。
内製か外注かを決める際には、以下の5つの観点でスコアリングすると整理しやすくなります。
この軸をもとにプロジェクトごとに採点すれば、どこを社内で持ち、どこを委託するかが明確になります。
フレームを用意しても、実際の現場では「経営層の意向」や「上司の好み」に流され、意思決定が先送りになるケースが多いです。
そのため、意思決定のルールを明文化することが重要です。
たとえば「競争優位性が低く、速度が最優先の領域は必ず外注する」といった社内ルールを設定しておくと、余計な議論を省けます。
チャネル設計に着手する際、最初にすべきは「現状の見える化」です。広告費、SEO流入数、ウェビナー参加者数など、チャネルごとの投資額と成果を数字で整理しましょう。
特に MQL→SQL→商談→受注 までの転換率を把握することで、どのチャネルがボトルネックかが一目で分かります。
次に行うのは、「どのチャネルを強化すべきか」仮説を立てることです。
ここで役立つのが 「成長余地 × 実行難易度」マトリクスです。
こうした整理をすることで、「広告に追加予算をかけるべきか」「SEO強化を優先すべきか」といった判断が客観的に下せます。
チャネルミックス設計では、必ず実験の余地を残すことが重要です。具体的には以下の手順で進めます。
この実験プロセスがないと、過去の慣習や上司の意見だけでチャネル配分が決まり、非効率な投資を続けてしまいます。
チャネル配分は一度決めたら終わりではなく、四半期ごとに見直すべきものです。例えば、広告CPAが急上昇しているのに予算を据え置きしてしまえば、CACは確実に悪化します。
逆に、SEOやCRM施策の成果が出始めたら、短期投資から中長期投資へシフトするチャンスです。
チャネル配分の見直しを「経営層との合意形成の材料」として活用できれば、マーケ部門の存在感も高まります。
マーケティング人材の採用や外部活用を進める際に、よく見られる失敗パターンがあります。
これらは単なる人材不足以上に、組織の成果を長期的に阻害する要因となります。本章では典型的なミスとその回避策を整理します。
求人票(JD: Job Description)に「戦略設計から広告運用、SEO、コンテンツ制作まで全部やってほしい」と記載してしまうケースは非常に多いです。
しかし、実際にこれをすべて高いレベルでこなせる人材はほとんど存在しません。
結果として候補者が集まらなかったり、入社後に過度な期待とのギャップで早期離職につながるリスクがあります。
回避策は、役割を明確に分けることです。
戦略設計を担う「プランニング人材」と、実行を支える「専門領域担当」を切り分け、必要に応じて外部のBPOや代理店を活用するほうが現実的です。
データ分析やCRO(コンバージョン改善)、CRM活用を担える人材がいない場合、意思決定が「過去の経験」や「上層部の勘」に偏りがちです。
これではチャネルごとの投資配分や施策評価が曖昧になり、マーケティング効率が低下します。
回避策は、最低限「数値を読み解ける担当者」を確保すること。
外部の分析支援を一時的に導入しても良いですし、社内で既存のデータを扱えるメンバーをトレーニングして兼任させる方法もあります。
重要なのは「感覚ではなく数値」で議論できる体制をつくることです。
多くの企業がCRMツールを導入しますが、導入後に運用が属人化してしまう失敗例が少なくありません。
担当者が退職・異動した途端に「誰も使えないツール」になり、結局Excelやスプレッドシートに逆戻りすることもあります。
回避策は、運用ルールと教育体制をセットで整えることです。
CRMは「入力・更新・活用」が定着して初めて成果を生みます。
週次レビューやレポーティングを組織に組み込み、属人化を防ぐ仕組みを持たせることが必要です。
さらに、ナレッジ移転型の外部支援を併用することで「使える状態を標準化」できます。
本記事では、IT/SaaS企業が直面する「マーケティング人材不足」の本質と、採用・外注活用における具体的な打ち手を解説しました。
単なる人数の不足ではなく、「戦略・プランニングができる上位人材の不在」と「データドリブンな意思決定の欠如」が成果未達の根本原因であることをご理解いただけたはずです。
また、要件定義のテンプレート、内製/外注判断フレーム、チャネルミックスの設計手順を提示しました。
これらを活用すれば、短期的な成果改善と中長期のナレッジ蓄積を両立させることが可能です。
マーケティングの人材不足は「待っていれば解決する」課題ではありません。
正しい要件定義とリソース配分設計を行い、外部の力を戦略的に活用することで、四半期内に成果を出すことができます。

記事を書いた人
アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。
関連記事