アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。

IT・SaaS企業のマーケ責任者必見。リソース不足や属人化で戦略が止まっていませんか?本記事では、マーケティング戦略外注の活用法、内製/外注の最適配分、3ヶ月で成果を出すロードマップを解説します。
目次
「マーケ人材は社内にいるはずなのに、施策が前に進まない」──IT/SaaS企業のマーケティング責任者からよく聞く声です。
広告やSEO、ウェビナーなど手を打ってはいるものの、数字につながらない。
経営層からは「四半期の売上・パイプラインをどう伸ばすのか」と詰められ、チームは日々の運用に追われて戦略的な意思決定ができないまま時間が過ぎてしまう。
実はこの停滞の正体は、「リソース不足」そのものではありません。
問題は、スキルの偏りとリソース配分の機能不全です。
広告に強いがコンテンツは弱い、分析できる人材がいない、業務が一部の担当者に集中して属人化するこうした状況では、どれだけ人がいても戦略は機能しません。
本記事では、IT/SaaS企業のマーケティング責任者に向けて、
を体系的に解説します。
記事を読み終える頃には、「なぜ動かないのか」から「どう動かすか」へと視点を転換でき、社内を説得できる具体的な材料(チェックリストやロードマップ)を持ち帰れるはずです。
SaaSマーケでは広告、SEO、ウェビナー、コンテンツなど多岐にわたるチャネルを同時に運用する必要があります。
しかし「広告は得意だがSEOが弱い」「コンテンツは作れるがデータ分析ができない」といったスキルの偏りがあると、施策が途中で止まり、全体最適ができなくなります。
特定の担当者に業務が集中してしまうと、引き継ぎが難しく属人化が進みます。
その結果、緊急タスクに振り回され、本来優先すべき施策の順序が崩れてしまいます。
施策は走っているのに、事業計画に直結しない「場当たり的な動き」になりがちです。
SaaS企業は投資家や経営層から四半期単位で成果を求められるため、常に時間的プレッシャーがあります。
しかし、戦略がKPIツリーと結びついていないと、経営層に示す根拠がなく意思決定が遅れ、施策も遅れてしまいます。
これが「数字に追われるが戦略が描けない」という負のループを生みます。
マーケ組織が「機能しているかどうか」を見極めるには、複雑な分析ツールは不要です。
以下の4つの観点でセルフチェックを行えば、15分で現状の課題が浮き彫りになります。
これらの問いに Yesが少ないほど、外部導入+戦略再設計の必要度は高い と言えます。
チェックリストを活用し、まずは自社の現状を数値と事実で可視化することが、改善への第一歩です。
診断によってリソースの偏りが明らかになったら、次は解決に向けたアクションです。
ここでは「優先順位を決める」「役割を仕分ける」「仕組み化する」という3つのステップで、戦略を前進させる方法を紹介します。
SaaSのマーケ施策では「やらないこと」を決める勇気が不可欠です。
広告・SEO・ウェビナー・展示会など、すべてを同時にやろうとすると中途半端に終わりがちです。
四半期で成果が見込めるチャネルに絞り込み、投資と工数を集中させることで短期的なインパクトを最大化できます。
リソース偏りを解消するには、内製と外注の線引きを明確にする必要があります。
この仕分けを行うだけで、現場が「どこまで自分たちでやるべきか」を迷わず判断できるようになります。
優先順位と役割分担が決まっても、仕組みがなければ再び属人化に逆戻りします。
そこで有効なのが以下の仕組み化です。
この3点を揃えることで、リソースの無駄が減り、組織として安定して成果を出せる体制が構築できます。
SaaS企業のマーケ責任者にとって「四半期で成果を出す」ことは避けられないプレッシャーです。
リソース偏りを解消し、外部の知見を取り入れることで、90日間で戦略と実行を前進させることが可能になります。
ここでは、3ヶ月で進めるべき具体的なステップを示します。
まずは現状を正確に把握することが出発点です。
広告、SEO、イベント、ウェビナーなど、現在の施策のリソース配分を棚卸しし、事業計画から逆算したKPIを定義します。
たとえば「Pipeline創出額」「MQL数」「SQL率」などを指標に設定し、次の四半期で達成すべき目標値を明確化します。
定義したKPIをもとに、注力すべきチャネルを決め、予算と工数を再配分します。SEOならコンテンツ制作、広告なら予算最適化、ウェビナーならリード獲得シナリオ設計など、具体的な施策を走らせます。
この段階では「やらない施策」をはっきりと決めることが重要です。投資を分散させず、成果につながるチャネルにリソースを集中させます。
施策を開始して1〜2ヶ月が経つと、初期の成果データが見え始めます。
ダッシュボードを用いて効果を可視化し、改善点を洗い出しましょう。
この検証をもとに次期計画にスムーズに接続することで、短期成果を一過性で終わらせず、持続的な成長へつなげられます。
できるだけ明確なロードマップを描くことです。これを経営層に提示することで、リソース調整や外部導入の意思決定が進めやすくなります。
外部リソースを導入する際に、経営層や上司から必ず求められるのが「費用感」と「契約形態の妥当性」です。
SaaS企業のマーケ責任者としては、金額だけでなく スピード感・リスク管理・成果物の明確さ を合わせて説明する必要があります。
ここでは代表的な契約形態と費用イメージを整理します。
準委任契約は、プロ人材が週数日〜常駐に近い形でマーケ施策を伴走するモデルです。
メリットは柔軟な修正が可能で、戦略策定から実行まで幅広くサポートしてもらえる点です。
請負契約は、あらかじめ決めた範囲の成果物(例:KPIツリー、チャネル配分表、90日ロードマップなど)を納品するモデルです。
進め方が明確で、成果物をもとに社内を説得しやすいのが特徴です。
外部導入を検討する際は「採用」「外注」「現状維持」の3択を比較するのが定番です。
| 項目 | 採用 | 外注 | 現状維持 |
| スピード感 | ✖(半年〜1年) | ◎(即導入可) | ✖(施策停滞) |
| コスト | 高(年収600〜900万+採用コスト) | 中(数十万〜数百万/月) | 0 |
| 確実性 | 中(スキルミスマッチのリスク) | ◎(専門スキルを即戦力投入) | ✖(課題解決せず) |
| 組織学習 | ◎ | ○(一部吸収可能) | ✖ |
この比較を提示することで、経営層への説明がスムーズになり、決裁が早まる可能性が高まります。
外部リソースの導入や戦略設計を進める際、SaaS企業のマーケ責任者が陥りやすい失敗にはいくつかのパターンがあります。
これらを理解し、事前に回避策を準備することで、四半期内に成果を出す確率が格段に高まります。
「四半期で成果を出さなければ」というプレッシャーから、複数の施策を同時に走らせがちです。
しかしリソースが分散し、結果的にどれも中途半端になるケースが多いです。
回避法:優先度の高い施策を最大3つに絞ること。経営層には「やらないことを決めた理由」を合わせて説明することで納得を得やすくなります。
「とりあえず広告を出す」「コンテンツを増やす」といった行動先行型の施策は、後から成果の評価ができず失敗しやすいです。
回避法:Pipeline額やMQL数など、数値で定義したKPIを必ず設定してから着手すること。
外注先に「戦略も実行も全部任せたい」と丸投げしてしまうと、責任の所在が不明確になり、成果が出ないまま時間だけが過ぎることがあります。
回避法:RACI(責任者・実行者・協力者・承認者)を使って、社内と外部の役割を明確に分けること。
一部の担当者が外部とのやり取りを独占してしまい、情報がチーム全体に共有されないケースがあります。
回避法:ダッシュボードや週次レビューを必須化し、進捗と学びを全員で共有すること。
IT/SaaS企業のマーケティング組織では、「人はいるのに施策が前進しない」という課題が繰り返し起こります。
その原因は単純な人材不足ではなく、リソースの偏りと機能不全 にあります。
本記事では、その解決策として以下の流れを解説しました。
リソースが偏っていても、戦略設計×外部リソース活用 によって、四半期内に成果を出すことは十分可能です。
まずは本記事の診断項目を使い、自社の現状を確認してみてください。
そのうえで、優先度の高い施策を絞り、役割分担を明確にすることが第一歩です。ロードマップを描けば、経営層への説明材料にもなり、意思決定をスムーズに進められます。
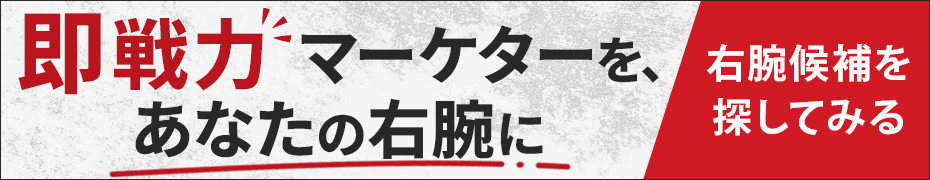
記事を書いた人
アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。