アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。
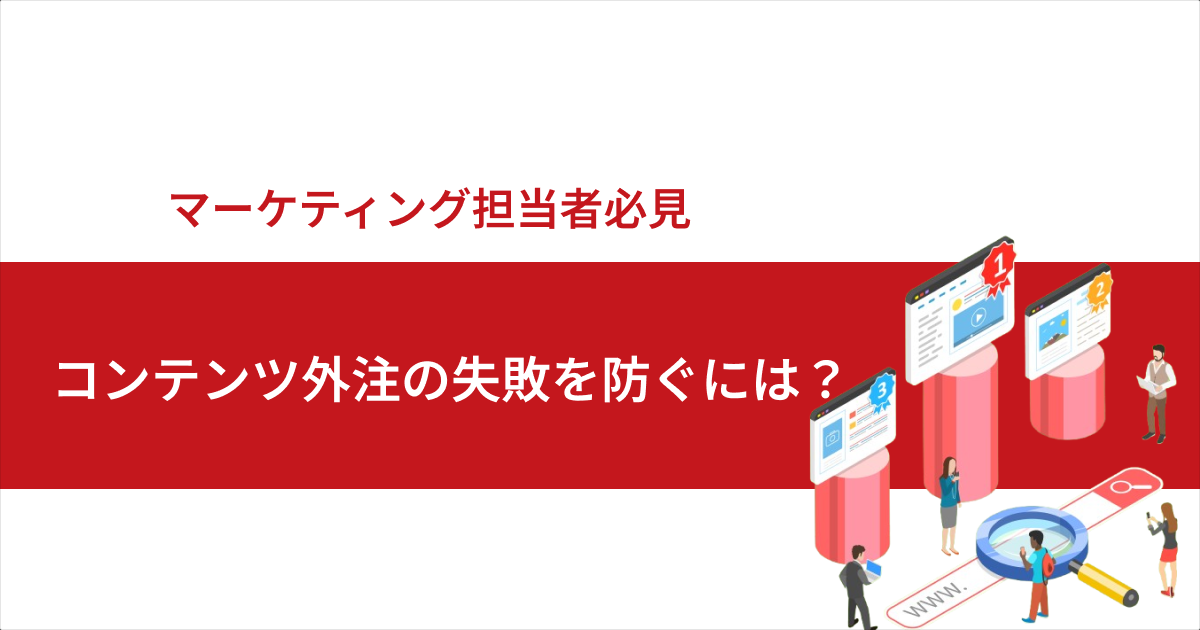
【SaaS企業向け】マーケティング外注・コンテンツ制作で失敗しない方法を徹底解説。外注設計の基本フレーム、KPI設計、役割分担の明確化など、成果を出すための仕組みづくりを具体的に紹介。代理店任せでノウハウが残らない、成果が安定しないといった課題を解決し、長期的なマーケティング資産を構築するための実践的ガイドです。
目次
SaaS企業のマーケティング担当者にとって、広告運用やコンテンツ制作の外注は避けて通れない選択肢です。
しかし、多くの企業が「代理店や外注に任せたのに成果が出ない」「外注コストばかり増えてしまった」といった課題に直面しています。特に従業員100〜500名規模の成長過程にあるSaaS企業では、マーケティング専任が2名以下というケースも珍しくありません。
その結果、外注設計の知識不足や仕組み化の不在が原因で、失敗を繰り返してしまうことが多いのです。
本記事では、以下の3つのメインテーマに沿って、外注活用における失敗の典型例と再発防止策を解説します。
SaaS企業のマーケティング担当者が、自社に最適な外注パートナーを選び、効果的に成果を生み出せるようになることを目的としています。
まず理解すべきは「外注設計=単なる発注業務」ではないということです。
外注設計とは、外部パートナーにどの範囲を委託し、どのような評価軸で成果を管理し、どのような社内体制で運用していくかを定義する仕組みのことを指します。
外注設計の段階で依頼内容を具体化できていないと、仕上がる成果物が想定と大きくかけ離れることがあります。たとえば「SEO記事を20本」という発注だけでは、記事テーマや検索意図、ペルソナに関する指示が不足し、表面的な情報を並べただけの文章が量産されがちです。結果として検索順位の向上やリード獲得には結びつかず、投下した予算に見合った成果を得られないという問題が起きやすくなります。
代理店に業務を全面的に任せ切ってしまうと、短期的には業務効率が改善するものの、社内に知見が蓄積されにくいという弊害があります。運用の意図や改善の背景を把握できないまま施策が進むため、いざ契約を終了した際に同じ水準の成果を再現できなくなるケースが多いです。担当者が学ぶ機会を失うことで、内製化や新しいパートナーへの切り替えが難しくなり、組織全体の成長を阻害してしまいます。
広告施策に頼り切ると、短期的なコンバージョンは伸びても、ブランド認知や自然検索流入といった長期的な資産が積み上がらないリスクがあります。成果指標を目先の数字だけに設定してしまうと、費用を投じ続けなければリード獲得が止まる不安定な状態に陥ります。その結果、顧客獲得コスト(CAC)は下がらず、継続的な成長戦略を描けないという状況を生み出してしまうのです。
これらの失敗は、発注先の問題ではなく、多くの場合は「外注設計の不足」によって引き起こされます。
特にSaaS企業で目立つのが、コンテンツ制作外注に関する失敗です。SEO記事、ホワイトペーパー、導入事例、ウェビナー台本など、制作物は多岐にわたりますが、外注化すると以下のような課題に直面しがちです。
外注でよくある問題のひとつが、依頼範囲を具体的に示せていないケースです。「SEO記事を10本お願いしたい」と伝えても、テーマの優先度や検索意図、狙うべき読者層を共有していなければ、外注先は一般的で広く浅い内容を選びがちです。
その結果、競合との差別化が図れず、見込み顧客に届かない記事が納品されることになります。リード獲得を目的にした施策であるにもかかわらず、実務上は形だけの納品に終わりやすいのが課題です。
コンテンツ制作において「記事数」や「納品本数」を成果指標に設定すると、制作物の量は増えても本質的な成果には結びつかない恐れがあります。
検索順位やクリック率、リード数などの指標を定めないと、質よりも納品ペースが優先され、評価基準も曖昧になりやすいのです。結果として、時間や費用を投じても成果が可視化されず、社内での評価や改善施策も打ちづらくなります。
外注パートナーとの間で製品理解やターゲット顧客の課題を十分に共有できていないと、制作物の内容にばらつきが生じます。コンテンツは一つひとつの品質も大切ですが、全体で統一感を持たせることでブランドの信頼性が高まります。
知識が断片的に伝わるだけでは、一貫性のあるコミュニケーションを実現できず、結果的に見込み顧客への訴求力が弱まってしまうのです。
外注を活用する場合、確認や修正依頼のやり取りに時間がかかりすぎると、社内担当者の負荷が大きくなります。連絡体制や承認フローを明確に決めないまま進行すると、納期が遅れたり、成果物の品質が下がったりする要因になりかねません。
本来は効率化を目的とした外注が、逆に担当者の業務を圧迫する事態を招きやすく、結果としてチーム全体の進行速度を落とすことになります。
整備されていないと、確認作業に時間がかかり、納期遅延や品質低下の原因になります。
では、こうした失敗をどう防げばよいのでしょうか。ポイントは「再現性を持った仕組み化」です。
外注設計を誤ると、期待と異なる成果物やノウハウの不在、さらに短期的な効果に終始してしまうといった問題が起こりやすくなります。
その結果、長期的に見ると自社の資産形成が進まず、継続的な成長が阻害されるリスクが高まるため、基本フレームの整備はとても重要な役割を担っています。
こちらでは外注設計の基本フレームでも重要なポイントについて解説します。
外注プロジェクトの成功には、社内チームと外部パートナーの役割分担を明確にすることが不可欠です。
自社のビジョンや市場理解が必要な企画・戦略立案は社内で、専門知識が求められる具体的な制作や運用は外注先に任せる分業体制を構築しましょう。
このように責任範囲を明確にすることで、互いが得意分野に集中でき、プロジェクト全体の効率が向上します。さらに、意思決定や承認フローも文書化することで、後々のトラブルを防ぎ、スムーズな進行につながります。
この明確な役割分担こそが、質の高いコンテンツを継続的に生み出すための鍵となります。
外注先の評価は、単なる作業量ではなく、ビジネス成果に直結するKPIを重視することが重要です。
例えば、記事の公開数だけでなく、「検索順位」「リード獲得数」「コンバージョン率」といった指標を設定しましょう。
これにより、外注先は単なる作業代行者ではなく、ビジネス目標を共有する戦略的パートナーへと意識が変わり、より質の高いアウトプットを生み出そうと努力するようになります。結果として、コンテンツ投資の費用対効果を最大化できるのです。
明確な成果指標を共有することで、双方の連携が強化され、プロジェクト全体の成功に繋がります。
外注プロジェクトで得た知見やノウハウを、組織の資産として活用するための「ナレッジ共有システム」を構築しましょう。
具体的には、プロジェクトの進捗や成功・失敗から学んだ教訓を文書化し、チームメンバーがいつでもアクセスできる仕組みを整備します。
これにより、特定の担当者しか知らないという「属人化」を防ぎ、組織全体の知識レベルが向上します。ナレッジが共有されることで、次のプロジェクトもより効率的に進められるでしょう。
外注パートナーとの協働を通じて得た学びを組織全体で共有することが、継続的な成長と改善を可能にする鍵となります。
外注をブラックボックス化すると、社内で実態が把握できず、品質管理や改善が滞りがちです。そのため、業務の流れをワークフローとして整理し、社内で見える化しておくことが求められます。
こうしておけば、担当者が変わってもスムーズに引き継げるだけでなく、進行状況や課題の発見も容易になります。透明性を高める仕組みは、外注パートナーとの信頼関係を築くうえでも大きな意味を持ちます。
外注を始める際に、いきなり大規模に展開すると失敗したときの損失が大きくなります。
まずは限定的な範囲で試験的に依頼し、その成果や課題を検証することが賢明です。テスト段階で得たデータをもとに改善を繰り返し、精度を高めながら徐々に範囲を広げることで、リスクを抑えた運用が実現できます。
このサイクルを継続することで、外注の再現性と成功確率を高められます。
外注を円滑に進めるためには、契約や運用のルールを標準化しておくことが大切です。
例えば、成果物の範囲や修正対応の回数、納期に関する取り決めを明文化しておくことで、トラブルを未然に防げます。こうしたルールを初期段階で共有しておくと、外注先との認識の齟齬が生まれにくくなり、業務を安定して進められるようになります。
結果として、双方にとって安心感のある協力体制が築かれるでしょう。
SaaS企業のコンテンツ外注における失敗は、外注設計の知識不足と仕組み化の欠如が原因です。
成功への道筋には、役割分担を明確化し、ビジネス成果に直結するKPIを設計することが鍵となります。企画・戦略は社内、制作・運用は外注先と分業することで、互いの強みを活かせます。
さらに、小規模テストから始め、検索順位やリード獲得数といった成果指標で評価することで、リスクを抑えつつ投資対効果を最大化できます。外注パートナーを戦略的協力者と捉え、継続的な改善を回すことが、長期的な資産形成に繋がるのです。
もし、貴社が「外注に頼っているが成果が安定しない」「代理店解約後の再現性に不安がある」と感じているなら、マーケティングリソースマネジメント(MRM)を取り入れることをおすすめします。
MRMを活用することによって、SaaS企業が持続的に成果を上げられる体制づくりをサポートしています。
広告運用やコンテンツ制作の「失敗を繰り返さない仕組み」を整えたい方は、ぜひ以下のバナーからお問い合わせください。

記事を書いた人
アイトリガー編集部
信頼できるデジタルマーケティングパートナーとして、クライアントとともに成長していくことを行動指針として活動する、プロフェッショナルなマーケター集団。実戦で得た経験をもとに、リアルな打ち手と課題解決のヒントをお届けします。